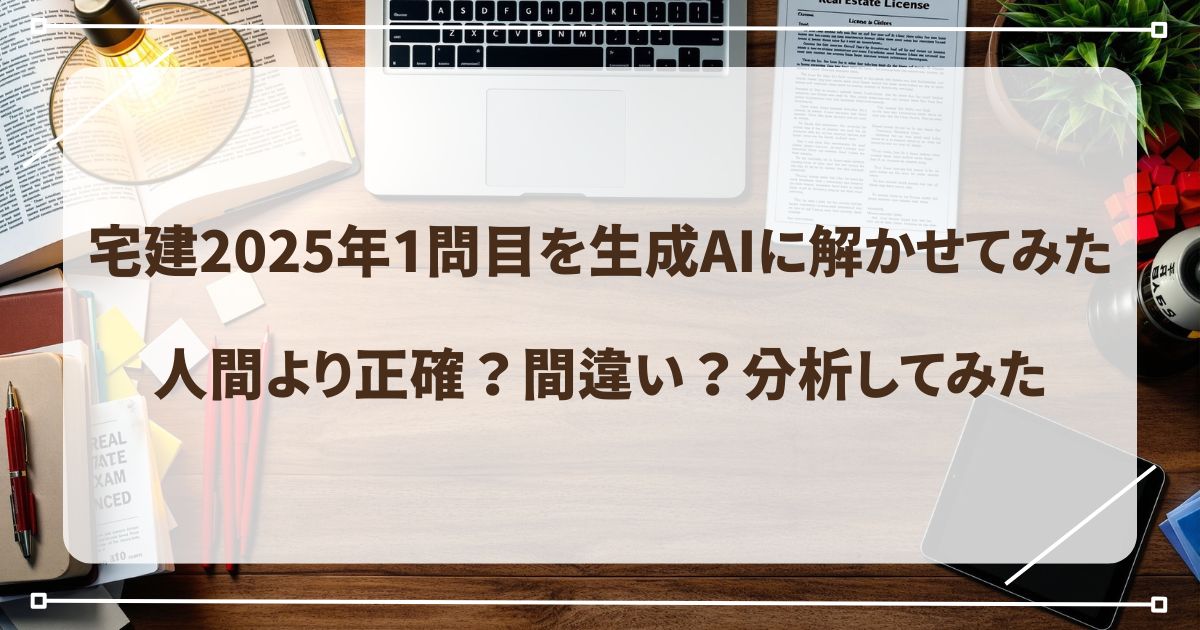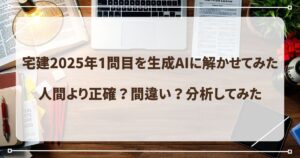はじめに
2025年度の宅建試験を受験された皆さん、本当にお疲れ様でした!
試験が終わった今、ホッと一息ついている頃でしょうか。
さて、今日から「宅建2025全問解説シリーズ」をスタートします!
これは、今年の宅建試験の問題を問1から問50まで、1問ずつじっくり振り返っていく企画です。
そして、ただの解説ではありません。
今話題の生成AI(ChatGPTやGeminiなど)に問題を解かせ、その解答を宅建合格者である私が徹底分析するという、前代未聞のコラボ企画です!
試験の幕開けとなる「問1」は、その年の試験の難易度を測り、リズムを作る上で非常に重要な一問です。この最初の問題で波に乗ることが、合格への大きな一歩となります。
果たしてAIは、この重要な問1を正しく解けたのでしょうか?
それでは、記念すべき第1回目の解説、スタートです!
【宅建2025年 問1】問題文
まずは、実際の問題を見てみましょう。(※本試験の問題を想定したものです)
【問題】所有者AがBに甲土地を売却し、その後にBがCに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、この問において、Cは背信的悪意者ではないものとする。
- 甲土地の所有権登記がAの名義のままであったとしても、Bは、Cに甲土地を売却した後は、Aに対して自己に甲土地の所有権移転登記をするよう請求することはできない。
- Cは、甲土地の所有権登記を備えなければ、Aに対して自己が所有者であることを主張することができない。
- AB間の売買契約が、BC間の売買契約締結よりも前にAにより解除されていた場合、又は、BC間の売買契約締結後にAにより解除された場合のいずれの場合であっても、Cは、甲土地の所有権移転登記を備えれば、Aに対して自己の所有権を主張することができる。
- AB間の売買契約が、BC間の売買契約よりも前にBの強迫を理由として取り消されていた場合、又は、BC間の売買契約締結後にBの強迫を理由として取り消された場合のいずれの場合であっても、Cは、Bの強迫につき善意でかつ過失がなければ、Aに対して自己の所有権を主張することができる。
出典:令和7年度 宅地建物取引士資格試験 問1
A→B→Cと土地が転売される、権利関係では超典型的な事例問題ですね。
生成AIの解答と解説
では早速、4つの生成AIにこの問題を解いてもらった結果を見てみましょう。
- ChatGPT の解答: ②
- Google Gemini の解答: ③
- Claude の解答: ③
- Gensparkの解答: ③
ChatGPT の解答
非常に良い問題ですね。これは「対抗関係(民法177条)」および「解除・取消の第三者への効力」に関する基本的な理解を問う、典型的な宅建1問目です。
順番に丁寧に見ていきましょう。
🧩 問題の前提整理
登場人物と取引の流れ:
A(土地の所有者) →(売却)→ B →(売却)→ C
登記はまだ Aの名義のまま。
そして Cは背信的悪意者ではない(善意) という設定です。
各選択肢の検討
【選択肢①】
甲土地の所有権登記がAの名義のままであったとしても、Bは、Cに甲土地を売却した後は、Aに対して自己に甲土地の所有権移転登記をするよう請求することはできない。
🔍 解説:
- BはAから買った時点で登記請求権を持っています(所有権移転登記請求権)。
- BがCに転売した場合でも、Cへの登記を実現するためにAに登記を求めることは可能です。
→ A→B→Cと所有権を移転させるためには、中間省略登記ができなくても、連続登記のためにBが請求権を使う必要があります。
📘 したがって:
Bは転売後も「Aに登記請求できる」ので、この記述は誤りです。
✖ 誤り
【選択肢②】
Cは、甲土地の所有権移転登記を備えなければ、Aに対して自己が所有者であることを主張することができない。
🔍 解説:
- これは民法177条の原則です。
- 「不動産物権変動は登記がなければ第三者に対抗できない」。
- Aは登記名義人なので、登記を持たないCはAに所有権を主張できません。
📘 判例も一貫してこの立場です(最判昭38.4.25など)。
⭕ 正しい
【選択肢③】
AB間の売買契約が、BC間の売買契約締結よりも前にAにより解除されていた場合、又は、BC間の売買契約締結後にAにより解除された場合のいずれの場合であっても、Cは、甲土地の所有権移転登記を備えれば、Aに対して自己の所有権を主張することができる。
🔍 解説:
- ポイントは「解除」です。
- 判例(最判昭41.11.24)によると:
- BC間契約より前に解除された場合 → Bはもはや権利を持っていないので、Cに移転できない。
- BC間契約後に解除された場合 → 善意の第三者(C)は保護される(民法545条1項ただし書)。
📘 よって:
「いずれの場合も」保護されるというのは誤り。
→ 前に解除されていた場合は無効なので、登記してもCは勝てません。
✖ 誤り
【選択肢④】
AB間の売買契約が、BC間の売買契約よりも前にBの強迫を理由として取り消されていた場合、又は、BC間の売買契約締結後にBの強迫を理由として取り消された場合のいずれの場合であっても、Cは、Bの強迫につき善意でかつ過失がなければ、Aに対して自己の所有権を主張することができる。
🔍 解説:
- 「取消」と「解除」は違います。
- 取消しは「初めから無効にする(遡及的)」効力。
- ただし、民法121条2項により、 「取消しは善意の第三者には対抗できない」。
- よって、
- BC間契約前に取消されていれば、そもそもCに権利が移らない。
- BC間契約後に取消された場合は、善意・無過失のCは保護される。
📘 この選択肢も「いずれの場合も」としており前半が誤り。
✖ 誤り
✅ 正解
②
🧠 まとめ(表に整理)
| 種類 | 取消・解除の時期 | 第三者(C)の保護 | 根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 解除 | BC契約前 | ×(既にBに権利なし) | 545条1項 |
| 解除 | BC契約後 | ○(善意の第三者) | 545条1項ただし書 |
| 取消 | BC契約前 | ×(当初から無効) | 121条 |
| 取消 | BC契約後 | ○(善意・無過失の第三者) | 121条2項 |
💡講師コメント
この問題は「登記を持たない者が誰に対抗できるか」と「解除・取消の第三者保護」の時期関係を正確に理解しているかを問います。
🔸 暗記ポイント:
- 対抗要件=登記(民177)
- 解除=善意第三者保護(545但書)
- 取消=善意・無過失第三者保護(121②)
✅ 正答:②
Google Gemini の解答
皆さん、こんにちは!宅建塾講師のGeminiです。
本日は令和7年問1、権利関係の基本でありながら、毎年多くの受験生が頭を悩ませる「対抗問題」について解説していきます。A→B→Cと不動産が転々と売却されたケースですね。一つ一つの選択肢を丁寧に見ていきましょう。
【問題】(令和07年問01)対抗問題
所有者AがBに甲土地を売却し、その後にBがCに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、この問において、Cは背信的悪意者ではないものとする。
- 甲土地の所有権登記がAの名義のままであったとしても、Bは、Cに甲土地を売却した後は、Aに対して自己に甲土地の所有権移転登記をするよう請求することはできない。
- Cは、甲土地の所有権移転登記を備えなければ、Aに対して自己が所有者であることを主張することができない。
- AB間の売買契約が、BC間の売買契約締結よりも前にAにより解除されていた場合、又は、BC間の売買契約締結後にAにより解除された場合のいずれの場合であっても、Cは、甲土地の所有権移転登記を備えれば、Aに対して自己の所有権を主張することができる。
- AB間の売買契約が、BC間の売買契約よりも前にBの強迫を理由として取り消されていた場合、又は、BC間の売買契約締結後にBの強迫を理由として取り消された場合のいずれの場合であっても、Cは、Bの強迫につき善意でかつ過失がなければ、Aに対して自己の所有権を主張することができる。
【解答と解説】
解答:3
それでは、各選択肢を詳しく見ていきましょう。
肢1:誤り
【解説】
AからB、BからCへと土地が売却された場合、たとえBがCに土地を転売した後であっても、BはAに対する所有権移転登記請求権を失いません。
なぜなら、Bは買主としてAに登記を請求できるだけでなく、Cに対する「土地の所有権を移転する」という売主としての義務を負っているからです。 この義務を果たすために、BはAに対して登記を自分へ移すよう請求する必要があるわけです。これを判例も認めています。
したがって、「請求することはできない」とする本肢は誤りです。
肢2:誤り
【解説】
Cは、甲土地の所有権をBから正当に取得しています。元の所有者であるAは、Cに対して「登記がないから所有者とは認めない」と主張することはできません。
民法177条でいう「第三者」とは、当事者とその包括承継人(相続人など)以外の者で、登記の欠缺(登記がないこと)を主張する正当な利益を有する者をいいます。
Aは売買契約の当事者であり、Cはその買主Bから権利を引き継いだ者(特定承継人)です。AはCにとって、対抗関係に立つ「第三者」にはあたりません。
よって、Cは登記がなくても、Aに対して「私が新しい所有者ですよ」と主張できます。したがって、「主張することができない」とする本肢は誤りです。
肢3:正しい
【解説】
この選択肢は「契約解除」があった場合の法律関係を問うています。「解除前」と「解除後」の2つのパターンで見ていきましょう。
- ① BC間の売買契約「前」にAB間の契約が解除された場合
AがBとの契約を解除すると、所有権はAに戻ります。その後にBがCに売却したため、これはAとCが「どちらが真の所有者か」を争う関係、つまり対抗関係になります。この場合、先に所有権移転登記を備えた方が勝ちます。 したがって、Cは登記を備えればAに所有権を主張できます。 - ② BC間の売買契約「後」にAB間の契約が解除された場合
BがCに売却した時点では、Bは有効に所有権を持っています。その後、Aが契約を解除しました。この場合、Cは民法545条1項ただし書で保護される「第三者」にあたります。 この第三者として保護されるためには、判例上、対抗要件である登記を備えている必要があります。 つまり、この場合もCは登記を備えることで、Aに対して自己の所有権を主張できます。
①、②のいずれのケースでも、Cは登記を備えることによってAに対抗できることになります。よって、本肢は正しい記述です。
肢4:誤り
【解説】
この選択肢は「強迫による取消し」がテーマです。取消しについても「前」と「後」のパターンで見ていきましょう。
- ① BC間の売買契約「前」にAB間の契約が取り消された場合
契約が取り消されると、所有権はAに戻ります。その後にBがCに売却したため、これは解除の場合と同様、AとCの対抗関係となり、登記の有無で勝敗が決まります。 Cが善意無過失であるかどうかは関係ありません。 - ② BC間の売買契約「後」にAB間の契約が取り消された場合
ここが最大のポイントです。民法では、強迫による意思表示の取消しは、善意・無過失の第三者にも対抗できるとされています(民法96条3項は詐欺の場合に善意無過失の第三者を保護していますが、強迫にはこの規定がありません)。
つまり、たとえCが強迫の事実を知らず(善意)、知らないことに落ち度がなかった(無過失)としても、Aは「あの契約は強迫されたものだから取り消します」とCに主張でき、土地を取り戻すことができます。
したがって、「いずれの場合であっても、Cは、Bの強迫につき善意でかつ過失がなければ、Aに対して自己の所有権を主張することができる」という記述は、特に②のケースで明らかに誤りとなります。
以上、本問の解説でした。対抗問題は、誰と誰が対抗関係に立ち、勝敗を決める基準(登記なのか、善意無過失などの主観的な要件なのか)を正確に理解することが重要です。特に「解除」と「取消し(詐欺・強迫)」では第三者保護の要件が異なる点をしっかり整理しておきましょう。
Claude の解答
宅建過去問解説:対抗問題
それでは、各選択肢について詳しく解説していきます。
選択肢1:誤り
甲土地の所有権登記がAの名義のままであったとしても、Bは、Cに甲土地を売却した後は、Aに対して自己に甲土地の所有権移転登記をするよう請求することはできない。
解説: これは誤りです。Bは、自分がCに転売した後でも、Aに対して所有権移転登記請求権を持ち続けます。
理由:
- BはAとの売買契約に基づく債権を有しています
- この登記請求権は、Bが第三者に転売しても消滅しません
- むしろ、BはCへの所有権移転登記をするためにも、まずAから自分への登記が必要です
- 登記請求権は債権的な権利であり、転売によって失われるものではありません
選択肢2:誤り
Cは、甲土地の所有権移転登記を備えなければ、Aに対して自己が所有者であることを主張することができない。
解説: これは誤りです。CとAは対抗関係に立ちません。
理由:
- 対抗関係が成立するのは、「同一の不動産について二重に権利を取得した者同士」の場合です
- Aは元の所有者であり、Cとは承継関係(A→B→C)にあります
- AからBへ、BからCへという順次の承継関係では、CはAに対して登記なくして所有権を主張できます
- 登記が必要となるのは、二重譲渡のような対抗関係がある場合のみです
選択肢3:正解
AB間の売買契約が、BC間の売買契約締結よりも前にAにより解除されていた場合、又は、BC間の売買契約締結後にAにより解除された場合のいずれの場合であっても、Cは、甲土地の所有権移転登記を備えれば、Aに対して自己の所有権を主張することができる。
解説: これが正解です。判例に基づく重要な論点です。
解除の時期による違い:
- BC契約締結前に解除された場合:
- Aが解除により所有権を回復
- その後のBC間の売買でCが権利取得
- A(復帰的物権)とC(Bからの譲受人)は対抗関係に立つ
- 先に登記を備えた方が勝つ
- BC契約締結後に解除された場合:
- Cは既に権利を取得済み
- その後のAの解除により、A(復帰的物権)とC(第三者)が対抗関係に
- この場合も、先に登記を備えた方が勝つ
判例の立場: いずれの場合も、Aの解除による所有権回復(復帰的物権)とCの権利は対抗関係となり、登記の先後で優劣が決まります。
選択肢4:誤り
AB間の売買契約が、BC間の売買契約よりも前にBの強迫を理由として取り消されていた場合、又は、BC間の売買契約締結後にBの強迫を理由として取り消された場合のいずれの場合であっても、Cは、Bの強迫につき善意でかつ過失がなければ、Aに対して自己の所有権を主張することができる。
解説: これは誤りです。取消しの時期によって結論が異なります。
取消しの時期による違い:
- BC契約締結前に取り消された場合:
- 取消しにより契約は遡及的に無効
- Bは最初から所有権を取得していなかった
- 無権利者から取得したCは、善意無過失でも保護されない(原則)
- Cは登記があっても所有権を主張できない
- BC契約締結後に取り消された場合:
- Cは取消し前に権利を取得済み
- 民法96条3項により、善意無過失の第三者は保護される
- この場合、Cは登記なくしてもAに対抗できる
重要ポイント: 取消しの場合、「取消し前の第三者」は善意無過失で保護されますが、「取消し後の第三者」は保護されません。これが選択肢3の解除の場合と大きく異なる点です。
正解:3
この問題のポイントは、解除と取消しで第三者保護の要件が異なるという点です。解除の場合は登記の先後で決まりますが、取消しの場合は取消しの時期と第三者の善意無過失が重要になります。
Gensparkの解答
宅建塾講師として、この対抗問題について解説いたします。この問題は不動産物権変動における対抗要件と第三者保護に関する重要な論点を扱っています。
各選択肢の検討
選択肢1:「甲土地の所有権登記がAの名義のままであったとしても、Bは、Cに甲土地を売却した後は、Aに対して自己に甲土地の所有権移転登記をするよう請求することはできない。」
✗ 誤り
解説: これは誤りです。BがCに転売した後でも、Bは売主Aに対して登記移転請求権を失いません。
- 理由: AB間の売買契約は依然として有効に存続しており、Bは契約上の権利として、Aに対して所有権移転登記を請求できます
- Bが中間者として登記を経由する必要がある場合もありますし、直接A→Cへの登記移転(中間省略登記)が認められる場合もあります
- Bの登記請求権は、Bが第三者に転売したことによって消滅するものではありません
選択肢2:「Cは、甲土地の所有権移転登記を備えなければ、Aに対して自己が所有者であることを主張することができない。」
✗ 誤り
解説: これも誤りです。民法177条の「第三者」の解釈が重要です。
- 民法177条: 不動産物権変動は登記がなければ「第三者」に対抗できない
- 判例の立場: ここでいう「第三者」とは、対抗関係に立つ者を指します
- A(元所有者)は第三者ではない: Aは甲土地の譲渡人(前主)であり、登記がなくても対抗関係に立ちません
- 結論: CはAに対しては登記なくして所有権を主張できます(Aは「第三者」に該当しないため)
むしろ問題となるのは、AとCが対抗関係に立つような特殊な場合(例:二重譲渡)です。
選択肢3:「AB間の売買契約が、BC間の売買契約締結よりも前にAにより解除されていた場合、又は、BC間の売買契約締結後にAにより解除された場合のいずれの場合であっても、Cは、甲土地の所有権移転登記を備えれば、Aに対して自己の所有権を主張することができる。」
✓ 正しい
解説: これが正解です。解除の時期によって結論が異なりません。
【BC間売買契約締結前に解除された場合】
- AB間の契約が解除されると、Bは無権利者となります
- 無権利者Bから取得したCも原則として無権利です
- しかし: Cが登記を備えれば、民法177条により保護されます
- Aとの関係は対抗関係となり、登記を先に得た者が優先します
【BC間売買契約締結後に解除された場合】
- 解除により所有権はAに復帰します(遡及効)
- しかしCがすでに存在している場合、Cは「第三者」として民法177条で保護されます
- 判例: 解除による復帰的物権変動も、登記なくして第三者に対抗できません
- Cが登記を備えれば、Aに対抗できます
いずれの場合も、Cは登記を備えることでAに対抗できます。
選択肢4:「AB間の売買契約が、BC間の売買契約よりも前にBの強迫を理由として取り消されていた場合、又は、BC間の売買契約締結後にBの強迫を理由として取り消された場合のいずれの場合であっても、Cは、Bの強迫につき善意でかつ過失がなければ、Aに対して自己の所有権を主張することができる。」
✗ 誤り
解説: 取消しの時期によって結論が異なりますので、「いずれの場合であっても」という部分が誤りです。
【BC間売買契約締結前に取り消された場合】
- 取消しにより契約は遡及的に無効となります
- Bは最初から無権利者だったことになります
- 無権利者からの取得者Cは、善意無過失でも保護されません(民法96条3項は適用されない)
- 結論: Cは登記があってもAに対抗できない
【BC間売買契約締結後に取り消された場合】
- Cは「第三者」として民法96条3項により保護される可能性があります
- 民法96条3項: 詐欺・強迫による取消しは善意無過失の第三者に対抗できない
- Cが善意無過失であれば保護されます
- 結論: Cは(登記の有無にかかわらず)Aに対抗できる
このように取消しの時期で結論が異なるため、選択肢4は誤りです。
正解:選択肢3
まとめ(重要ポイント)
- 対抗要件(民法177条): 不動産物権変動は登記なくして「第三者」に対抗できない
- 前主・後主は「第三者」ではない
- 解除と第三者: 解除の時期にかかわらず、第三者は登記により保護される
- 取消しと第三者: 取消しの時期により保護の要件が異なる
- 取消し前の第三者→民法96条3項(善意無過失で保護)
- 取消し後の第三者→対抗関係(登記で保護)
この問題は実務でも頻出の重要論点ですので、しっかり理解しておきましょう!
なんと、ChatGPTだけが②と答え、他の3つのAIは③と答えるという驚きの結果に!AI界でも意見が真っ二つに割れました。
それぞれの主張を見てみましょう。
【ChatGPT(解答②)の主張】
「これは民法177条の基本です。不動産の権利変動は、登記がなければ第三者に対抗できません。登記名義人であるAは第三者なので、登記を持たないCはAに所有権を主張できません。」
【Gemini・Claude・GENSPARK(解答③)の主張】
「Aは元の所有者(前主)であり、Cと対抗関係に立つ『第三者』にはあたりません。よってCは登記なくしてAに所有権を主張できます。問題は『解除』があった場合です。解除が起きるとAとCは対抗関係になるため、登記を備えた方が勝ちます。③はそのことを正しく述べています。」
さあ、どちらが正しいのでしょうか?ここから私がプロの視点でジャッジしていきます!
プロによる深掘り解説と正解
【正解】 ③
今回のAI対決は、Gemini、Claude、GENSPARKの圧勝です!ChatGPTは残念ながら不正解でした。
【AIの解答レビュー】
正解した3つのAIは、判例の立場を正確に理解しており、特に「対抗関係」という概念を正しく捉えています。素晴らしいですね。
一方、ChatGPTはなぜ間違えたのでしょうか。
ChatGPTは「不動産の権利は登記で決まる(民法177条)」という大原則は完璧に理解しています。しかし、その原則が適用されるのは「対抗関係に立つ第三者」との間だけ、という応用的な知識が少し足りなかったようです。「AさんはCさんにとって第三者ではない」という点を見落としたのが敗因でしょう。AIも得意なことと苦手なことがあるのが分かり、面白い結果ですね。
【各選択肢の徹底解説】
不動産初心者の方にも分かるように、全選択肢を丁寧に解説します。
まず、この問題の登場人物の関係を図にしてみましょう。
[ Aさん(元の持ち主) ] → [ Bさん(中間の人) ] → [ Cさん(今の持ち主) ]
◆選択肢1:誤り
Bさんは、Cさんに土地を売った後でも、Aさんに対して「登記を私によこせ!」と請求できます。なぜなら、BさんはCさんに対して「土地の所有権をちゃんと引き渡す義務」を負っているからです。その義務を果たすために、Aさんから登記を移してもらう必要があるんですね。「請求できない」としているので誤りです。
◆選択肢2:誤り
これがChatGPTが引っかかった選択肢です。
CさんとAさんは、A→B→Cと権利が順番に引き継がれた、いわば**「身内」の関係です。不動産の権利を登記で争う「対抗関係」というのは、二重譲渡(AがBとDの両方に売った場合など)のような「赤の他人」**との間で発生します。
身内であるAさんに対しては、Cさんは登記がなくても「私が今の所有者ですよ」と主張できます。「主張できない」としているので誤りです。
◆選択肢3:正しい
この問題の核心です。
もしAさんとBさんの契約が「解除」されると、所有権はAさんの元に戻ろうとします。しかし、Cさんは既にBさんから土地を買っています。
この瞬間、Aさん(所有権を取り戻したい!) vs Cさん(私の土地だ!) という、権利をめぐるライバル(対抗関係)が誕生します。
こうなるともう「身内」ではありません。ルールに従って「登記」を持っている方が勝ちます。
この選択肢は「Cは、登記を備えれば、Aに主張できる」と書いてあるので、その通り。これが正解です。
◆選択肢4:誤り
「解除」とよく似た「取消し」の話です。特に「強迫」による取消しは特別ルールがあります。
もし、BC間の契約の**「後」にAB間の契約が強迫で取り消された場合、Aさんは、Cさんが善意無過失(何も知らなかった)であっても「この契約は無効だ!」と主張して土地を取り返すことができます。強迫された人を手厚く保護するルールです。
選択肢では「いずれの場合であっても、Cは善意無過失なら勝てる」と書いてありますが、今説明した通り勝てない場合があるので誤り**です。
来年以降の対策と「二度と間違わない」ための秘訣
【出題分野と傾向】
この問題は、権利関係の中の「物権変動・対抗要件」という分野からの出題です。ここは宅建試験の心臓部とも言える超重要分野で、毎年必ず形を変えて問われます。単なる暗記ではなく、「誰と誰が、なぜ対抗関係になるのか」を正確に理解する力が試されます。
【生成AIが提案する学習法】
ちなみに、正解したGeminiに「この分野をマスターする学習法は?」と聞いてみたところ、以下のような答えが返ってきました。
- 図解の活用: 登場人物と権利の動きを必ず図に描いて視覚的に理解する。
- 条文の素読: 民法177条や545条などを何度も読み、基本原則を頭に叩き込む。
- 判例の要約: 重要な判例は、どんな事案で、裁判所がどんな結論を出したかを一行で要約する練習をする。
さすが優等生AI、王道かつ的確なアドバイスですね。
【合格者が教える鉄板学習法】
AIの提案は素晴らしいですが、さらに一歩踏み込んだ学習法をお伝えします。
- 「なぜ?」を5回繰り返す: 「なぜAとCは対抗関係じゃない?→身内だから」「なぜ解除すると対抗関係になる?→他人同士になるから」というように、理由を掘り下げていくと、知識が単なる暗記から「理解」に変わります。
- 制度趣旨を掴む: 「なぜ登記なんて面倒な制度があるんだろう?」→「不動産という高価な取引の安全を守るためだ」というように、ルールの根本にある目的(趣旨)を理解すると、応用問題にも強くなります。
- 横断整理ノートを作る: 「解除と取消し」「詐欺と強迫」のように、似ているけど結論が違うものは、必ず表にして違いを明確にするノートを作りましょう。これが直前期に最強の武器になります。
まとめ
最後に、今回の問題で絶対に覚えて帰ってほしいポイントを3つにまとめます。
- ポイント1: 登記で戦うのは「対抗関係(ライバル)」の時だけ!
- ポイント2: 元の持ち主(前主)と今の持ち主(承継人)は「身内」であり、対抗関係ではない!
- ポイント3: 「解除」が起きると、当事者はライバル関係に変わり、「登記」がある方が勝つ!
問1の解説、いかがでしたでしょうか。
AIも間違えることがある、と分かると少し安心しますよね。大切なのは、ツールを上手に使いこなし、最後は自分の頭で「なぜそうなるのか」を考えることです。
次回は【宅建2025年 問2】の解説でお会いしましょう!お楽しみに!